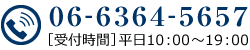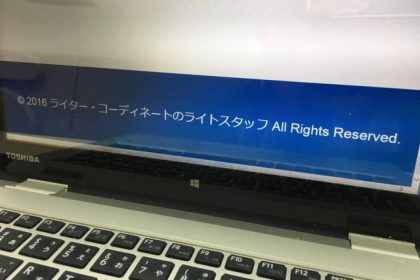ライターの原稿作成に文字おこしはマストか?
(ライター向け記事)
インタビュー取材をする際、ボイスレコーダーで録音するのは、取材で得た情報や話の因果関係などの正確性を担保するためです。極端な言い方をすれば、取材内容を理解し、細かな情報を正確に記憶しているなら録音を聞き返すことなしに原稿が書けます。まして文字起こしをする必要などありません。もちろん仕事の業務として文字おこし原稿の提出を(仕事の)依頼者から求められているのなら対応する必要はありますが。
インタビュー取材の録音データを必ず文字おこしするという人もいます。今は録音データをアプリやAIで活字化できる優秀なツールがあって便利ですが、それでも誤字は発生します。仕事として文字おこし原稿を受注している場合は、成果物として誤字をチェックしつつ文章を整え納品する必要があります。
しかし仕事の業務でもないのに、取材のメモ書きを元に記事を書けるのに、文字おこしを取材原稿作成の1つのプロセスとして踏むのは非効率です。それをしたほうが原稿を書きやすい、または原稿の質が上がるならするのがベターですが、本当にそうなのでしょうか? 非効率のみならず原稿の質を落とす原因になっていると私は考えます。
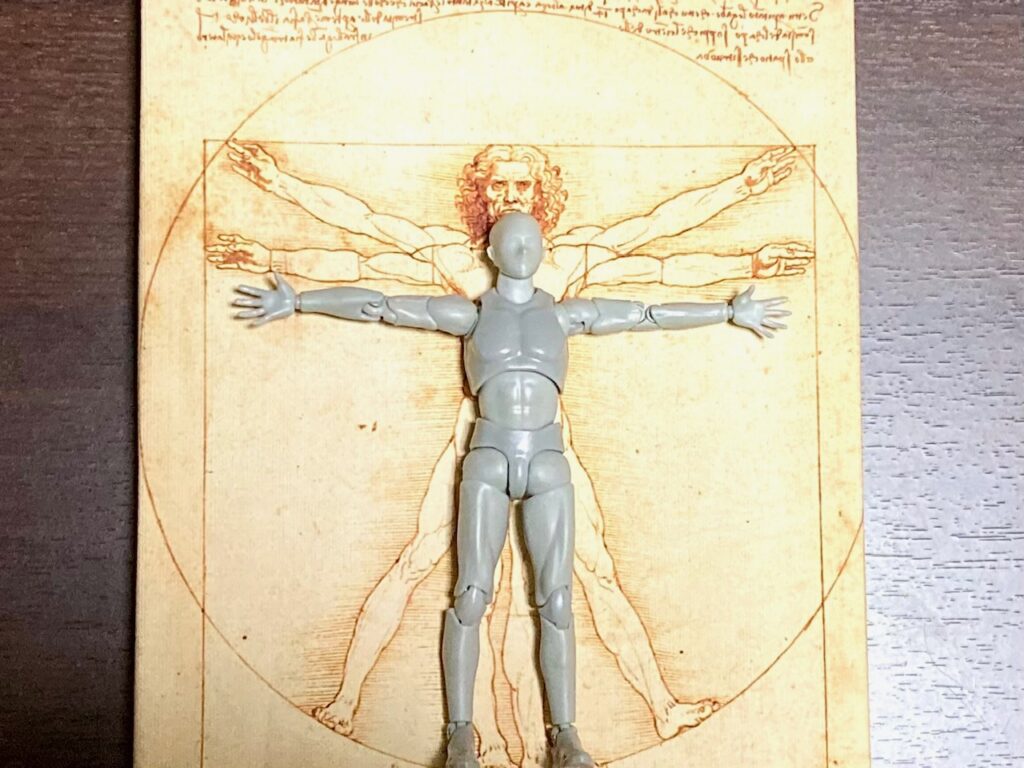
取材後すぐに原稿を書くな
私がライターの仕事を始めたのは2000年以降ですが、業界の先輩からは「取材後すぐに原稿を書くな」とアドバイスされたものです。駆け出しの頃、取材後すぐに原稿を書いて納品すると、書き直しを命じられることがよくありました。経験不足から来るニーズを外した内容や展開もありましたが、「取材対象を持ち上げ過ぎていて、読者は興ざめる」とよく指摘されました。
ライターが書く取材記事の多くは、その取材対象の魅力を伝えることが主な目的です。例えば、ある研究者の取材記事を書く場合、事前にその方の研究テーマや人となりをできる範囲で下調べをし、編集コンセプトをもとに質問を用意して取材に挑みます。記事を書くには、その取材対象に興味がないと良い情報収集や取材はできません。取材対象者にとっては、メディアを通じて自分を広報する絶好の機会なので多くはインタビュアーであるライターに対して好意的に接してくれます。
そういった事情も相まって取材した直後のライターは取材対象のファンになりがちです。その思いを原稿にしたためたいという衝動に駆られ、そのテンションのまま原稿を書くと、「取材対象を持ち上げ過ぎていて、読者は興ざめる」と編集者やディレクターからダメ出しを食らいます。だから「取材後すぐに原稿は書くな」「少し時間を置いて冷静な気持ちになってから原稿を書きなさい」と言われたものです。
数日間熟成させてから書け
私事ではありますが、取材記事を書くときに文字おこしはしません。もちろんボイスレコーダーで取材を録音します。それも2台同時に作動させます。万一に1台が機械トラブルで作動しなくなった際の保険です。取材後、私も原稿を書きたい気持ちでいっぱいになります。取材しながら記事をイメージするので、取材後には記事内容とざっとした構成が出来上がっていて、忘れないうちに原稿を書きあげたい、「鉄は熱いうちに打て」そんな気持ちが支配します。
先述したように取材後すぐに書く原稿の質は良くないことを経験的に知っているので、あえて原稿作成には取り掛からず、他の業務をしながら時おり取材のことを思い出したり、頭の中で記事構成を考えたりします。数日経つと取材の記憶がデフォルメされていることに気が付きます。印象に残ったものはより明確になり、取材直後に見えていなかったものが見えるようになっています。反対に印象の薄いものは記憶から消えつつあります。その状態でプロットを考えて、原稿を書き上げます。
そんな主観的な心理状態で正確な記事が書けるのかと思われるかも知れませんが、取材時に相手の言っていることが理解できているのなら書けるはずです。書けないのは、相手(取材対象)の話を理解できていないか、十分な取材ができておらず原稿を完成させるだけの有益な情報を得られていないか、よほどその取材内容に関心を持てなかったかのどれかです。
記憶に残った事柄でライター自身が取材対象の物語を紡ぐと枝葉末節の情報は淘汰され、本質的な事柄を客観的かつドラマチックに伝える内容になります。ここで言うドラマチックとは読者が記事に引き込まれるほど、興味深く読めることであって、先述した取材対象を持ち上げる(=ドラマチックに書く)という意味では決してありません。
古今の優れた書き手は、書ける状態にあってもしばらく放置し、機が熟すのを待ちます。そのことを「熟成」と表現します。ワインを円熟した味わいに変化させるためにしばらく樽の中で寝かせる「熟成」と同様に書きたいとはやる気持ちを抑えてしばらく寝かせ円熟させるという比喩表現です。
発言の切り貼りは映像編集。文字媒体の特権を使え
「文字おこし原稿=取材対象者の発言」をベースに記事を書き上げるのはライターの仕事ではありません。発言を部分的に切り取り、前後関係を入れ替え、いいあんばいにするのは映像媒体の手法です。映像媒体の場合、(インタビューの)取材対象者が発した言葉を違う言葉に置き換えることはできません。AIを使えば技術的に可能でしょうが、それは偽造です。しかし活字媒体においては、取材対象者の言葉のニュアンスをより明確に、読者に伝わりやすく言い換えたり、言葉足らずなところを補足したりすることはインタビュー記事作成の定石です。
取材対象者の発した言葉をそのまま活字にすると議事録のようになってしまい、内輪でしか通用しない内容になってしまいます。そのことを見越して、読者に伝わるように取材対象者の発した言葉の真意や背景をも活字で述べる必要があります。実際に発した言葉を活字にすると50字だったとしても、その言葉の真意を伝えるには200字必要になることもあります。
取材対象者の表現をそのまま使わず変更することは相手に対して失礼だと考える人もいますが、決してそんなことはありません。ニュアンスや真意がより読者に伝わるなら、編集者のみならず取材対象者にも喜ばれます。言葉の言い回しにとらわれるのではなく、その言葉の真意を活字化するのがライターの役割です。
以上のことから文字おこし原稿をベースにして書くと議事録のような内輪にしか通用しない内容、すなわち読者にとって非常に分かりづらくなることをご理解いただければ幸いです。
ライターの仕事は、取材で得た情報を自分なりに理解し、話の真意がより伝わるように工夫しながら再編集して活字化することだと私は考えます。取材記事ではありますが、各ライターが自身の感性とテクニックで創作する、ある種の物語と言えます。
【関連ブログ】
ライター的ボイスレコーダーの使い方
https://www.writer.co.jp/voicerecorder/
☆↓ライターを探している担当者さま
https://www.writer.co.jp/writer-coordination/
☆↓仕事を探しているライターさま
https://www.writer.co.jp/message1/
****************************************************
ライター手配のライトスタッフ
◆オフィシャルサイト:https://www.writer.co.jp/
◆ライターとの出会いをサポート:https://www.writer.gr.jp/
◆電話でのお問い合わせ:06-6364-5657
◆メールでのお問い合わせ:https://www.writer.co.jp/inquiry/
◆住所:〒530-0055 大阪府大阪市北区野崎町1-25新大和ビル207
****************************************************