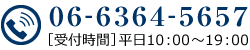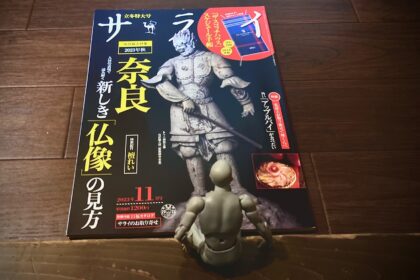生成AIを敬遠するライターさんに向けて
(ライター向け記事)
私の感覚ですが、生成AIを積極的に活用しているライターさんは1~2割、残りの8~9割のうち使っているまたは使ったことがあるが半分、まったく使ったことがないが半分。生成AIに頼っていない(活用していない)ライターさんが案外多いことに驚きます。
生成AIを使ったことがない人の中には「これまでに使う機会が無かった」または「興味がない」「必要性を感じない」と無関心な人もいれば、中には「生成AIを使って文章を書くようになればライターの存在意義が無くなる」と生成AIを“パンドラの箱”(=触れてはいけないもの)のようにとらえる人もいます。
確かに使い方によっては、ライターの存在意義を否定したり、ライターとしての技術や体力を後退させる懸念はあります。しかし現時点において、生成AIが優れたライターさんに太刀打ちできるとは思いません。
例えば、ライターではない人が編集者やクリエイティブディレクターからインタビュー記事の指示を受けて、その人がインタビューし生成AIを使って書いた記事と、優れたライターさんが生成AIを使わずに書いた記事とでは、後者のほうが良い記事になるだろうとライターの方やライターと一緒に仕事をしている方なら容易に想像がつくと思います。
編集者やクリエイティブディレクターの意図や媒体の性質を考慮したインタビューと執筆(の工夫)がライターにはでき、ライターでない人にはできないからです。そう考えると(文章作成に関して言えば)生成AIはあくまでツールであり、使用する人の知識や技術に大きく委ねられるとご理解いただけると思います。
インタビュー取材を終えた時点で、ライターなら記事の構成や落としどころが直感的に見えたり、「今回は一筋縄では行かない」と感じたりします。それはその記事に関して、何が正解で何が不正解であるかを感覚的に理解しており、いっぽうライターでない人にはそれが分かりません。生成AIを文章作成に使うにしても、その土台(=直感的に見えた記事の構成や落としどころ)の上にもっと良い可能性は無いかと模索することなので、生成AIの使用がライターの存在意義を自ら否定するなどということはありません。

記事作成ではなく、情報収集や理解を深めるために使う
前述したようにライターと(ライターではない)一般の人とでは、生成AIを使って文章作成するという概念そのものが違うと考えます。どんな構成でどんな展開でどんな落としどころにすれば良いかと無策で生成AIに尋ねるライターはいないでしょう。もしライターがそんな使い方をすれば、それこそがライターの存在意義を自ら否定することになります。
ライターの生成AIの使い方として堅実で効率的なのは、情報の整理をしたり執筆する情報をより理解するために使うことです。検索エンジンではたどり着けなかったり、たどり着くのに時間がかかることが、一瞬にしてたどり着けることがあります。
私ごとですが、20年ほど前に作家の故藤本義一さんとお話する機会がありました。その時に、藤本さんから「ウイスキーの水割りをハイボールと名付けたのは僕や」と聞き、とても印象的でそのすぐ後、インターネットで検索したもののその情報にたどり着けなかったことがありました。最近そのことを不意に思い出し、生成AIのGeminiに以下の内容を聞きました。
※≪≫は私がGeminiのプロントに入力した質問文です。
≪作家の藤本義一さんと話す機会があり、その時に藤本さんがウイスキーの炭酸割りを「ハイボール」と名付けたのは自分だとおっしゃっていました。しかし古い映画『カサブランカ』で主演のハンフリーボガードがバーで「ハイボール」とオーダーするシーンがあります。藤本さんは私に嘘を言ったのでしょうか?≫
(上記質問に対するGeminiの回答)
結論から申し上げると、藤本義一さんがあなたに嘘を言ったわけではないと考えられます。この「ハイボール」という言葉を巡る話には、いくつかの側面があります。
【「ハイボール」という言葉の語源】
「ハイボール」という言葉の起源には諸説ありますが、最も有力なのは19世紀後半のイギリスやアメリカで生まれたという説です。当時、ゴルフのハイボール(高く上がったボール)に似ているから、あるいは鉄道の信号で使われた「ハイボール(高い位置にある球体)」にちなんでいるなど、様々な説があります。
いずれにしても、ウイスキーのソーダ割りという飲み方と「ハイボール」という名称は、少なくとも20世紀初頭には既に欧米で広く知られていたことが確認されています。そのため、1942年公開の映画『カサブランカ』でハンフリー・ボガートが「ハイボール」とオーダーするシーンがあっても全く不思議ではありません。
【日本での「ハイボール」の定着】
藤本義一さんがおっしゃった話は、おそらく日本国内での「ハイボール」の呼称を指していると思われます。
戦後、日本のバーや居酒屋ではウイスキーをストレートや水割りで飲むのが主流でした。その中で、藤本義一さんを含む文化人や作家たちが、ウイスキーをソーダで割る新しい飲み方を広めようとしました。
藤本義一さんは、その当時あまり一般的でなかったウイスキーのソーダ割りに「ハイボール」という呼び名を定着させる上で、大きな役割を果たした人物の一人です。彼が執筆した作品や、参加した文化人との交流を通じて、この呼び方が日本の大衆にも広まっていきました。
【まとめ】
藤本義一さんが「自分がハイボールと名付けた」とおっしゃったのは、「日本にハイボールという呼び方を広めたのは自分だ」という文脈だったと解釈するのが自然です。決して、世界で初めてハイボールという言葉を生み出した、という意味ではないでしょう。
彼は、日本の飲酒文化において、ウイスキーのソーダ割りを「ハイボール」と呼び、それを一般に浸透させる立役者の一人であったことは間違いありません。この言葉の起源と、日本での定着の歴史は別物であり、藤本さんのお話はそのうちの後者だったと考えられます。
以上。
20年越しのこの疑問に対して、納得感のある回答をしてくれたGeminiに感動をしつつ、そこで湧き出た率直な下記の疑問をプロンプトに入力しました。
≪ありがとうございます。こちらの回答はネットの情報からですか? それともネット情報をもとに導き出したのですか?≫
(上記質問に対するGeminiの回答)
ありがとうございます。ご質問への回答は、インターネット上の複数の情報源(記事、専門サイト、辞書、個人のブログなど)を総合的に分析し、その内容を基に構成したものです。具体的には、以下の点が主な情報源となっています。
【「ハイボール」の語源に関する情報】
ゴルフ説、鉄道説、グラスの形状説など、諸説あることを示す情報。これらの説は古くから存在し、日本よりもはるか以前の欧米で広まっていたことが分かります。
これらの情報は、サントリーなどの企業サイトや、お酒に関する専門サイト、学術的な辞典など、複数の信頼できる情報源で確認できます。
【藤本義一さんに関する情報】
藤本さんが日本のウイスキー文化、特にハイボールの普及に貢献したという逸話。彼が作家仲間や文化人とウイスキーのソーダ割りを広めた、という話は、日本の酒文化史を語る上でよく取り上げられるエピソードです。
彼が「ハイボール」という言葉を日本に定着させる上で果たした役割は、多くの記事や伝記的な情報で語られています。
これらの情報を組み合わせて、ご質問の「なぜ藤本義一さんの話と映画『カサブランカ』のシーンが矛盾しないのか?」という問いに答えるために、世界的な「ハイボール」の歴史と日本における「ハイボール」の歴史を区別して説明するという形で、回答を導き出しました。
つまり、単にネットの情報をコピー&ペーストしたのではなく、複数の情報から共通する事実や文脈を抽出し、ご質問の意図に合わせて論理的に再構成したものです。
以上。
上記Geminiの回答を受けて、私の生成AIの仕組みに関する知識と合致しないところを確認するために、これまでの自分の認識をプロンプトに入力しました。
≪生成AIは、次にどんな言葉が来るかの確率論で文章を組み立てるので、ネット上に存在する情報から組み立てると思い、情報から新たな解釈を導き出すことはないと思っていました。≫
(上記質問に対するGeminiの回答)
ご指摘の通り、生成AIが「次にどんな言葉が来るか」を確率的に予測して文章を組み立てているというのは、その仕組みの本質を捉えています。しかし、そこから「ネット上に存在する情報のコピーしかできない」という結論にはなりません。
【「新たな解釈」を生み出す仕組み】
生成AIは、単に情報をコピーするだけでなく、学習した膨大なデータの中から、異なる情報を組み合わせて新しい文脈を作り出すことができます。これは、人間が複数の本や記事を読んで、それぞれの知識を統合し、新しい視点や結論を導き出すプロセスに似ています。
たとえば、次のような流れで「新たな解釈」が生まれることがあります。
【複数の情報源を統合する】
あるトピックについて書かれた複数の記事(歴史書、専門家の論文、個人のブログなど)を学習します。
【共通点と相違点を抽出する】
それぞれの情報源が持つ、共通の事実や異なる視点を認識します。
【論理的な関係を構築する】
それらの情報から「因果関係」「比較」「対比」といった論理的な関係を見つけ出します。
【新しい文脈で再構築する】
これらの関係性に基づいて、元の情報源にはなかった新しい説明や視点を生成します。
このプロセスは、完全にゼロから新しい真実を創造するわけではありませんが、既存の情報から新しい組み合わせや論理的な繋がりを見出し、それを分かりやすい言葉で表現することができます。これは、人間が「この情報とあの情報を合わせると、こんな風にも考えられるな」とひらめく作業に似ています。
このため、生成AIは単なる「データベース」ではなく、「情報統合エンジン」として機能し、ユーザーの質問に応じて、既存の知識から新しい文脈や解釈を導き出すことができるのです。
以上。
私の生成AIの仕組みに関する知識は限定的で、固定観念があったと知りました。生成AIと人間の思考処理は根本的に違うものだと考えていたので、驚きつつ以下の質問をプロンプトに入力しました。
≪人間と同じような導き出し方ですね。その技術は以前、一般に生成AIが公開された当初からあるものなのですか?≫
(上記質問に対するGeminiの回答)
その能力は、生成AIの初期のバージョンから基本的な形で存在していました。しかし、その精度と洗練度は、モデルの進化とともに飛躍的に向上しています。
【初期段階の生成AI】
初期のモデルは、膨大なテキストデータから単語や文の出現確率を学習し、その統計に基づいて文章を生成していました。例えば、「猫」の次に「が」が来る確率、「が」の次に「可愛い」が来る確率といった形で、パターンを単純に模倣していました。この段階でも、与えられたプロンプトに対して、学習した情報を組み合わせて新しい文章を作ることは可能でした。しかし、その文章はしばしば論理的に破綻したり、事実と異なる内容を含んだりすることがありました。
【近年の進化】
近年では、Transformerという技術の登場と、より大規模なデータでの学習により、AIは単なる単語の羅列ではなく、文脈全体を理解し、より複雑な論理構造を構築する能力を身につけました。この進化により、以下のようなことが可能になりました。
【複数の情報源からの統合】
異なるトピックや視点を持つ複数の情報を関連付けて、一つの coherent(まとまりのある)な回答を生成する。
【推論と要約】
提示された情報から結論を導き出したり、複雑な内容を簡潔にまとめたりする。
【文脈に応じた応答】
質問の意図や背景をより深く理解し、適切な応答を生成する。
このため、初期のAIと比較すると、現在のモデルはより人間らしい「思考」や「解釈」を行っているように見えるのです。これは、あくまで統計的なパターン認識の高度化によるものですが、結果として情報の統合・再構築能力が格段に向上しています。
以上。
ご覧いただいたように生成AIを使うと短時間で深い知識を得ることができ、執筆中に出てきた事柄について生成AIに質問し回答を得ることで、それを加味した情報にアレンジすることができ、使い方によっては内容に深みを持たせたり、より本質的なことに迫ることも可能になります。
「それを自力でするのがライターというものだ」と思われる方もいるかも知れません。それに反論させてもらうと、自力で内容に深みを持たせ、本質的なことに迫ることができたとします。生成AIを使えば、さらに一歩踏み込んだ内容になる可能性が高く、またより効率的に原稿作成できる可能性も高くなると考えます。
ライターにとって生成AIは決して「代筆マシーン」ではなく、執筆するうえで知りたい情報を深掘りして教えてくれる優秀な「デジタル秘書」であり、決してライターの存在意義を脅かすものではありません。
※【訂正】本文中に「古い映画『カサブランカ』で主演のハンフリーボガードがバーで『ハイボール』とオーダーするシーンがあります。」は、後日確認したところ、『カサブランカ』ではなく『市民ケーン』(1941年)のレストランのシーンでした。その作品にはハンフリーボガードは出演しておりません。大変失礼しました。
【関連ブログ】
現状において生成AIはライターの脅威なのか?
https://www.writer.co.jp/aikyouii/
☆↓ライターを探している担当者さま
https://www.writer.co.jp/writer-coordination/
☆↓仕事を探しているライターさま
https://www.writer.co.jp/message1/
****************************************************
ライター手配のライトスタッフ
◆オフィシャルサイト:https://www.writer.co.jp/
◆ライターとの出会いをサポート:https://www.writer.gr.jp/
◆電話でのお問い合わせ:06-6364-5657
◆メールでのお問い合わせ:https://www.writer.co.jp/inquiry/
◆住所:〒530-0055 大阪府大阪市北区野崎町1-25新大和ビル207
****************************************************